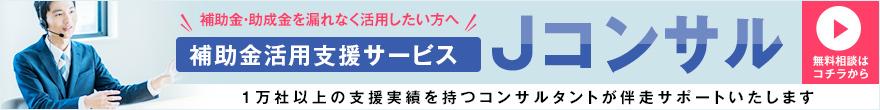社員の健康管理できてる?法令遵守すべき項目と取り組み16選

従業員の健康管理は、企業にとって欠かせない経営課題の一つです。
働く人々の健康を守り、安心して働ける環境を提供することは、生産性の向上や離職率の低下、企業イメージの向上につながります。また、経済産業省が推奨する「健康経営」は、従業員の健康を経営戦略の一環として捉え、持続的な成長を目指す新しいアプローチです。
本記事では、企業が法令で義務付けられた健康管理のポイントや、健康経営のメリット、さらに実践できる具体的な取り組み例をご紹介します。
▽この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。
1.企業に義務付けられた従業員の健康管理

中小企業を含む全ての企業は、従業員の健康を守るために法令で定められた義務を果たす必要があります。
これは労働安全衛生法を中心に、企業が職場環境を整備し、従業員の健康を維持・増進するための最低限の基準を定めたものです。ここでは、企業が遵守すべき主な健康管理義務について解説します。
🔵健康診断
企業は、労働安全衛生法第66条に基づき、常時雇用する労働者に対し年に1回の定期健康診断を実施する義務があります。
正規従業員は全員が健康診断実施の対象です。非正規雇用の従業員の場合、正規従業員の労働時間の4分の3以上を勤務しているアルバイト・パート社員は、健康診断の実施対象となります。
健康診断費用が福利厚生費として扱われるためには、従業員全員が健康診断を受診できる体制になっていること・健康診断が常識的な範囲の費用内で実施されていること・企業が医療機関に直接費用を支払っていることなどが条件となります。
🔵ストレスチェック制度の導入
50人以上の従業員を抱える事業所では、年に1回のストレスチェックを行う義務があります。
メンタルヘルス不調の予防や職場改善を目的とし、従業員が自分のストレス状況を把握するための重要な取り組みで、実施結果は個人情報として厳密に管理される必要があります。
ストレスチェックの内容は、国が推奨する質問事項を参考にすると良いでしょう。
🔵長時間労働の是正
法定労働時間とは、労働基準法第32条で定められている労働時間のことをいい、1日8時間、週40時間が原則とされています。
「36協定」と言われる法定労働時間を超えて残業をさせることを認める旨の「時間外労働・休日労働に関する協定書」を労働者・使用者間で締結した場合においても、時間外労働は月45時間・年360時間を超えることはできません。
月80時間超の時間外労働は過労死ラインとされ、過労による健康被害や精神障害が発生するリスクが高くなるとされています。
🔵安全衛生管理体制の整備
職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境を形成することを目的として、労働基準法の特別法である労働安全衛生法が定められています。
仕事で病気やけがをした場合は、労災保険給付の対象になります。仕事が原因の病気には、長期間にわたる長時間の業務による脳・心臓疾患や人の生命にかかわる事故への遭遇などを原因とする精神障害なども含まれます。
また、職場のパワーハラスメント・性別による差別・セクシュアルハラスメント・障碍者への差別の禁止や、合理的配慮の提供の義務など、職場環境の整備も義務付けられています。
🔵仕事と家庭の両立
仕事と家庭の両立を図りながら、充実した職業生活を送れるように、妊娠・出産、育児、介護をサポートし、働く男性、女性とも仕事を継続できるような制度が設けられています。
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性が休業を申請した場合または産後8週間を経過しない女性については、就業させてはならないほか、産後は原則として子どもが1歳(一定の場合は1歳6か月)になるまで、男性・女性とも育児休業を取得することができ、事業主は要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできません。
その他、介護休業は、対象家族一人につき、要介護状態に至るごとに1回、最長で通算93日間取得することができます。この場合も事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申出を拒むことはできません。
これらの家庭の事情による休業を取得したことを理由に、従業員を解雇するなどの不利益取り扱いすることは禁止されています。
🔵有給休暇の付与
年次有給休暇とは、所定の休日以外で、賃金の支払いを受けて仕事を休める日のことです。
半年間継続して雇用されている労働者は、全労働日の8割以上を出勤していれば、10日間の年次有給休暇を取ることができ、勤続年数が増えていくと、8割以上の出勤の条件を満たしている限り、1年ごとに取れる休暇日数は増えていきます。(20日が上限)
有給休暇は、原則として、休養のためでもレジャーのためでも利用目的を問わず取得することができ、アルバイト(パートタイム労働者)でも、[1]6か月間の継続勤務、[2]全労働日の8割以上の出勤、[3]週5日以上の勤務、という3つの要件を満たせば、正社員と同じだけ有給休暇が付与されます(週4日以下の勤務であったとしても、週の所定労働時間が30時間以上であれば、正社員と同じだけ有給休暇が付与されます)。
2.経済産業省が推奨する「健康経営」とは
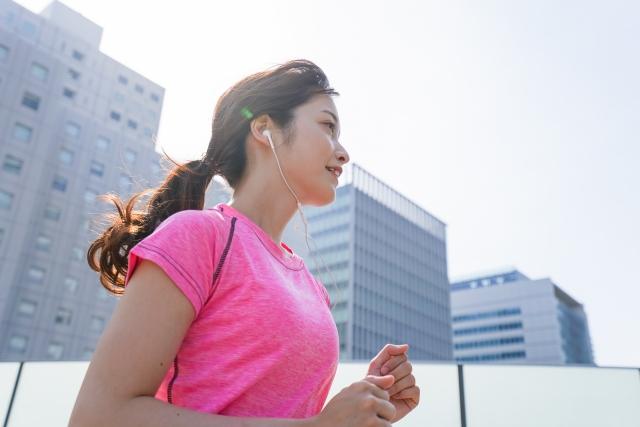
「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に取り組むことを指します。
これは、経済産業省が推進する健康投資の一環であり、企業が従業員の健康維持・増進を重視することで、組織全体の活性化や経営基盤の強化を図る考え方です。
具体的には、従業員の健康管理を単なる福利厚生の一環とするのではなく、企業の生産性向上やブランド価値向上につなげる「経営戦略」として位置づけます。経済産業省と日本健康会議は、健康経営に積極的に取り組む企業を評価・認定する「健康経営優良法人制度」を設け、取り組みを後押ししています。
▽この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。
3.従業員の健康管理を目的とした取り組み例17選

企業が従業員の健康管理を推進するためには、多様なアプローチを組み合わせることが重要です。以下では、具体的な取り組み例を16個ご紹介します。
🔴勤務場所と時間の選択肢の拡大
リモートワークやフレックスタイム制を導入し、従業員が柔軟に働ける環境を提供します。これにより、通勤によるストレスや身体的負担が軽減され、ワークライフバランスの向上につながります。また、体調に合わせた勤務スケジュールの調整も可能です。
🔴定期面談で心身の特性に応じた職種の選択
定期的な面談を実施し、従業員の健康状態やストレスレベルを把握した上で、適切な職務配置を行います。特に、精神的負担の大きい業務を軽減するための配置転換や業務内容の見直しが重要です。
🔴安否確認システムの導入
災害時や緊急時に備え、従業員の安否を迅速に確認できるシステムを導入します。このシステムは、災害だけでなく、従業員の安全や健康状態を把握する日常的なツールとしても活用可能です。
🔴福利厚生の充実
健康診断の費用負担や、フィットネスクラブの利用補助、健康相談窓口の設置など、従業員が健康を維持・向上できる福利厚生を充実させます。特にメンタルヘルスサポートのためのカウンセリング制度は重要な施策の一つです。
🔴運動イベントの開催
ウォーキングチャレンジやランニング大会などの運動イベントを定期的に開催し、従業員が楽しみながら運動習慣を身につけられる機会を提供します。チーム制で取り組むことで、職場内のコミュニケーション活性化にも寄与します。
🔴研修やセミナーの実施
ストレス管理や健康維持に関する研修やセミナーを開催します。例えば、健康的な食事の選び方、睡眠の質を高める方法、ストレス解消法など、実践的な内容を提供することで、従業員の健康意識向上を促します。
🔴安全の為の設備投資
職場の安全性を高めるために、作業環境の改善を行います。例えば、立ちっぱなし・座りっぱなしを防止する椅子やデスクの導入、防音設備や空調システムの整備など、従業員が安心して働ける環境を整えます。
🔴健康データの可視化と活用
ウェアラブルデバイスや健康管理アプリを活用し、従業員が自分の健康データ(歩数、心拍数、睡眠時間など)を可視化できる仕組みを導入します。これにより、健康意識を高めるとともに、企業側もデータに基づいた健康支援を行うことが可能です。
🔴禁煙サポートプログラム
禁煙外来の費用補助や、職場内全面禁煙の実施、禁煙チャレンジイベントの開催など、喫煙者が禁煙に成功できる環境を提供します。これにより、従業員の健康リスクを低減できます。
🔴メンタルヘルスケアプログラム
従業員がストレスを軽減できるよう、カウンセラーとの個別相談やグループセッション、オンラインメンタルヘルスプログラムを提供します。また、リラクゼーションスペースの設置も効果的です。
🔴健康経営の指標設定と公表
健康経営の取り組み効果を数値化し、従業員や外部に向けて公表することで、企業の姿勢を明確化します。たとえば、欠勤率、健康診断受診率、運動イベント参加率などをKPIとして設定します。
🔴健康食品や軽食の提供
社内の自販機やカフェテリアで、栄養バランスの良い食品や軽食を提供します。これにより、従業員が手軽に健康的な食生活を維持できる環境を整えます。
🔴リフレッシュ休暇の導入
一定期間ごとに取得できるリフレッシュ休暇制度を設けることで、従業員が心身をリフレッシュする時間を確保します。これにより、モチベーションと生産性が向上します。
🔴職場内コミュニケーションの促進
健康と働きがいを両立させるため、ランチミーティングやグループワークを通じて職場内のコミュニケーションを促進します。チーム内の信頼関係を深めることで、心理的安全性が高まります。
🔴ハラスメント防止対策
ハラスメントの防止は、従業員のメンタルヘルス保護に直結します。相談窓口の設置や、社内研修の実施を通じて、健全な職場環境を維持します。
🔴職場で睡眠環境の整備
昼休み中に短時間の仮眠が取れるスペースや、静かな休憩室を設置します。従業員が疲労を回復しやすい環境を整えることで、パフォーマンスが向上します。
4.従業員の健康管理を行うメリット

🔴離職率の低下
健康に配慮した職場環境は、従業員の体調悪化を未然に防ぎ、従業員の満足度を向上させ、離職率の低下につながります。
また、従業員を大切にする姿勢が評価され、求職者にとって魅力的な職場として映ることで、優秀な人材の採用や定着が実現できます。
🔴生産性の向上
従業員の健康状態が良好であれば、集中力やパフォーマンスが向上します。
特に、体調不良やメンタルヘルスの問題による欠勤や遅刻が減少することで、業務効率が大きく改善します。
また、従業員が健康に働ける環境を提供することで、エンゲージメントが高まり、自発的な働きが期待できます。
🔴企業のイメージアップ
従業員の健康管理に取り組む企業は、社会的責任(CSR)の一環としても評価されます。
特に「健康経営優良法人」の認定を受けることで、取引先や顧客からの信頼度が高まり、企業ブランドの向上につながります。これにより、新たなビジネスチャンスの獲得が可能になります。
▽この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます。
🔴社会保険料の負担軽減
従業員が病気の予防や早期発見に取り組むことで医療費が抑えられると、企業全体で支払う健康保険料率が安定し、従業員の長期休職や障害による公的給付が少なくなります。
少子高齢化による社会保険料負担が右肩上がりに増える中、企業ごとの健康管理の成果が広がれば、将来的に保険制度全体の見直しや優遇措置の導入が期待できるかもしれません。
5.まとめ

従業員の健康管理は、企業の基盤を支える重要な取り組みです。法令遵守を徹底し、安全で健康的な職場環境を整えることはもちろん、健康経営の視点を取り入れることで、企業価値の向上や競争力の強化が期待できます。
本記事で紹介した取り組みは、規模や業種を問わず、どの企業でも応用可能です。従業員一人ひとりが健康であることが、企業全体の成長につながる大きな力となります。
今こそ、健康管理に積極的に取り組み、働く人と企業が共に笑顔になれる環境を実現しましょう。
▽中小企業・個人事業主向けの補助金・助成金申請に関する無料相談窓口はこちら
※おすすめ研修
株式会社はな商店の提供する研修
ご相談はこちら→ https://lms.jirei.jp/hana/