2025年4月施行|育児休業給付金の拡充ポイントと労務担当者が留意すべき対応
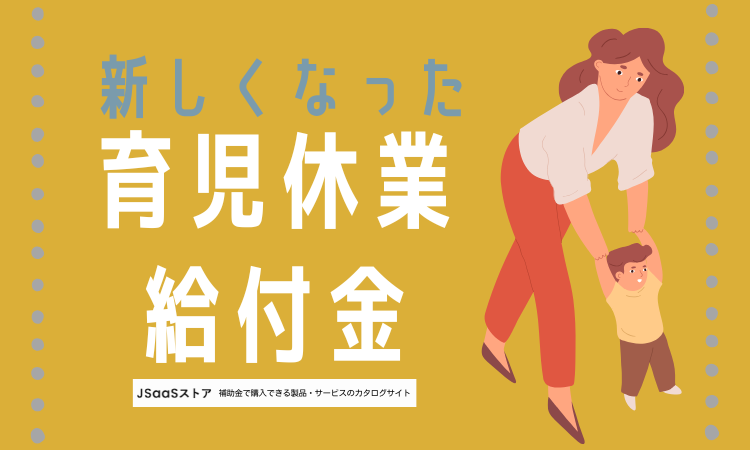
はじめに:2025年4月1日、育児休業給付が変わります!
2025年4月1日から育児休業給付金の制度が大幅に変更されます。少子化対策や仕事と育児の両立支援を目的としたこの改正は、労働者だけでなく、企業の労務担当者にも大きく関わる内容です。
この記事では、改正の背景と目的をわかりやすく解説し、労務担当者が押さえておくべきポイントや、企業が準備すべき実務対応について詳しく紹介します。
この記事でわかる事
- 育児休業給付金の改正内容と背景
- 労務担当者が押さえておくべきポイント
- 企業が行うべき実務対応と準備
育児休業給付金とは

育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、雇用保険から支給される給付金です。育児休業中の生活の安定を図り、安心して育児に専念できるように、国が用意している制度です。
雇用保険の被保険者であるアルバイトやパート従業員も一定の条件を満たせば給付対象となり、夫婦で分担して育児休業を取得することも可能です。
2025年3月までの規定では、原則産後休業終了後から1歳の誕生日まで(両親がともに育児休業を取得する場合や、保育所に入れないなどの場合は、最長2歳まで延長できる場合があります)の期間、標準報酬日額の67%が給付されます。
労務担当者が押さえておくべき2つのポイント
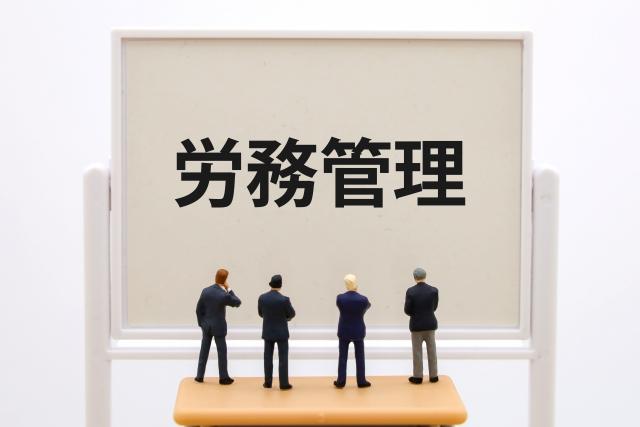
2025年4月1日より、育児休業給付金制度に大きな変更が加えられます。これにより、より多くの労働者が安心して育児休業を取得し、仕事と育児の両立を図れるようになることが期待されています。
ここからは労務担当者が抑えておきたいポイントをまとめます。
給付率と対象期間など変更点
【給付率】
🔵2025年3月末までは、賃金額の約67%
🔴2025年4月1日からは、賃金額の約67%(育児休業給付金)+出生後休業支援給付金(最大28日間、賃金額の約13%)で、最大28日間は賃金額の約80%(手取りで約10割)
【対象期間】
🔵2025年3月末までは、育児休業期間中
🔴2025年4月1日からは、出生後、父母それぞれ一定期間(父親は出生の日から8週間を経過する日の翌日までなど)
.png) 画像出典|育児休業給付案内リーフレット
画像出典|育児休業給付案内リーフレット
【その他】
🔴2025年4月1日からは、育児時短勤務給付の創設(育児のために短時間勤務を行い、収入が減少した場合に、減少分を補填)が予定されています
申請手続きの変更点
【手続き】
🔵2025年3月末までは、育児休業開始前に雇用主に申請、その後、雇用主がハローワークに手続きを行う。
🔴2025年4月1日からは、出生後休業支援給付金(夫婦ともに育児休業を取得した場合に追加給付される新設制度)・育児時短勤務給付(育児のために短時間勤務を行い、収入が減少した場合に、減少分を補填)については、新たに申請が必要になる可能性がある。
企業に求められる準備

企業において、社内規定の見直しと社内向け説明会の実施は、法令遵守や業務効率化、従業員の意識改革など、様々な目的のために重要な取り組みです。
これらの活動が効果的に行われるよう、具体的な実務対応と準備について解説します。
社内規定の見直し
社内規定の見直しは、企業が法令順守を徹底し、業務効率化を図り、リスクを管理し、そして企業文化を醸成するために不可欠な作業です。労働基準法をはじめとする関連法令の改正に対応するため、定期的に規定を見直す必要があります。
また、業務フローの変更や新しいシステムの導入など、企業を取り巻く環境の変化にも合わせて、規定を適宜修正していくことが求められます。
社内向け説明会の実施
育児休業給付金の拡充は、従業員にとって大きなメリットとなり、より多くの従業員が育児休業を取得しやすくなる可能性があります。
しかし、制度の変更に伴い、従業員には様々な疑問や不安が生じる可能性があります。そのため、制度の理解促進のため、社内向けの説明会を実施するとよいでしょう。
給付額のシミュレーション

2025年4月から、育児休業給付金制度が大きく変更になり、出生後休業支援給付金が新設されました。この変更により、育児休業中の収入が大幅に改善されるケースが出てきます。
【 Aさんの月収が30万円の場合】
🔵2025年3月末まで: 育児休業中の月額給付額は約20万円(30万円×67%)
🔴2025年4月以降(出生後休業支援給付金あり)
-
- 最初の28日間は、月額約24万円(30万円×80%)
- 29日目以降は、月額約20万円(30万円×67%)
上記のように2025年4月以降に申請した方は、出産後28日間は、従来よりも月額約4万円多く受け取れる可能性があります。ただし、出生後休業支援給付金は、夫婦ともに育児休業を取得した場合に受け取れます。
まとめ

2025年4月の育児休業給付金の改正は、労働者の育児と仕事の両立を支援するための重要な施策です。
労務担当者は、改正内容をしっかり把握し、企業として適切な対応を行うことで、従業員が安心して育児休業を取得できる環境を提供しましょう。
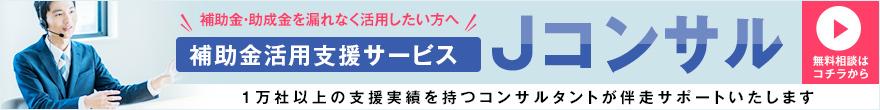
※おすすめ研修
IT Cross株式会社
ご相談はこちら→ https://lms.jirei.jp/it-cross/
