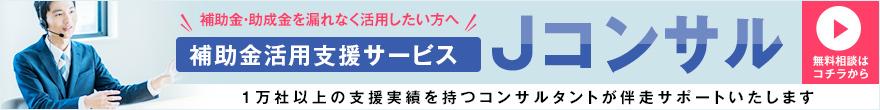カスハラ対処マニュアルで従業員を守る!制作ポイントを抑えて現場に活かす
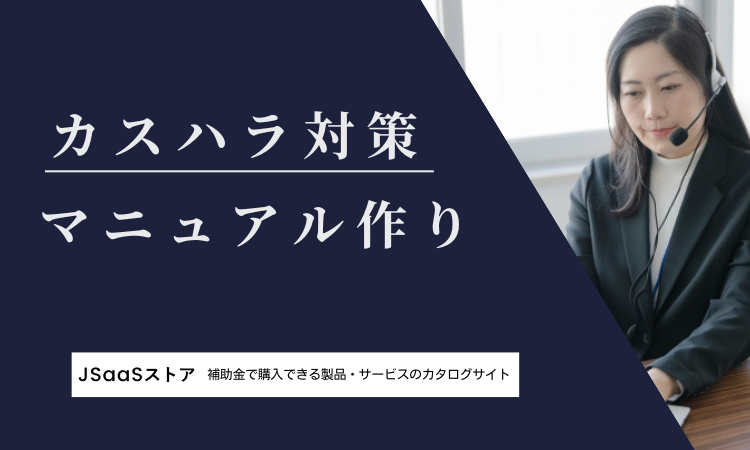
近年、顧客からの理不尽な要求や暴言といった「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を是正するため、法調整が進められるなど、議論が進んでいます。
本記事では、多くの企業や従業員が悩まされているカスハラの影響を解説し、従業員や企業の持続的な成長を守るためのマニュアル作成のヒントをまとめました。
▽補助金・助成金申請に関する無料相談を実施中!
1. カスハラとは

「カスタマーハラスメント」通称カスハラは、顧客や取引先などから、過剰な要求や商品・サービスに不当な言いがかりをつける悪質なクレームを受けることを指します。
商品やサービス等への改善を求める正当なクレームとは異なり、不条理で妥当性を欠く内容のクレームや、暴言・暴力・嫌がらせ、社会理念上不当な言動などがカスハラに該当します。厚生労働省が実施した「令和2年度職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間に顧客等から著しい迷惑行為を受けた企業の割合は19.5%、1度以上のカスハラを経験した労働者は15%となり、こうした行為に悩む企業・労働者が少なくありません。
2.「悪質なクレーム」を見分けるポイント
.png)
正当なクレームと悪質なクレームを見分けることはカスハラ対策にとって重要な課題です。事実関係の確認や要求内容の妥当性、要求の仕方や目的などの内容をしっかりと精査し、判断することが大事です。悪質なクレームとされる2つの特徴を見てみましょう。
クレーム内容が妥当性を欠く場合の例
- 商品やサービスに過失が認められない場合
- 企業の商品やサービス内容とは関係ない内容のクレーム
要求が社会通念上不当な言動の例
【要求の内容の妥当性に関わらず不相当とされる可能性がある言動】
- 身体への攻撃(暴行・傷害)
- 精神への攻撃(暴言・脅迫・中傷・名誉棄損)
- 威圧的な言動
- 強要行為
- 執拗な言動
- 差別的な言動
- 性的な言動
- 不退去・居座り
- 従業員個人への攻撃
【要求の妥当性と照らし合わせて不当とされる可能性がある言動】
- 金銭保証の要求
- 商品交換の要求
- 謝罪の要求
2.カスハラ対策に対するマニュアルが必要なワケ

カスハラ対応マニュアルを作成することは、従業員を守るだけでなく、企業の評判向上にもつながる重要な取り組みです。
それぞれの業種・業態に合わせ、実用的なマニュアルを作ることで、従業員への影響・時間の浪費・金銭的損失・業務上の支障・ブランドイメージの低下・他の顧客への被害等を軽減することが出来ます。
従業員への影響
カスハラへの対応を担当する従業員は、特に精神的な負担が大きいため、企業として毅然とした対応が必要です。
- 威圧的な言動や暴力などで従業員の心身を傷つける
- 特定の従業員への付きまとい
- 従業員へのわいせつ行為や盗撮被害
- 労災や離職などの割合が増加
上記のようなハラスメントが原因で業務パフォーマンスの低下や、健康不良、現場への恐怖感や苦痛による配置転換、休職、退職に至ってしまうことがあります。
時間の浪費
カスハラによる顧客対応の時間の浪費には以下のような事例があります。
- 長時間、従業員を拘束する
- 居座り行為
- 長時間の電話
- クレーム対応により通常業務に支障を及ぼす
クレーム現場での顧客対応や、電話での応対、謝罪の訪問、社内での対応方法の検討、弁護士への相談など、カスハラ対応で多くの時間と労力を消費してしまいます。
金銭的損失
企業の金銭的損失は、金銭の他にも対応時の人件費・外部の専門家への相談費用も含まれます。
- 言いがかりによる金銭要求
- 私物の故障について金銭要求
- 難癖をつけ未払い・代金の返金を要求
- 備品を過度に要求
- 通常業務が行えないことによる収入減
このほかにも商品やサービスの値下げ要求や慰謝料への対応、代替え品の提供で金銭的損失が発生する場合もあります。
業務上の支障
カスハラ対応によって業務が滞り、通常の業務が阻害されることも問題です。
- 度重なるクレーム・複数部署にまたがる複数回のクレームにリソースが奪われる
- 制度上対応できないことへの要求
- 優位な立場にいることを利用した暴言・特別扱いの要求
- 業務スペースなどへの不法侵入
カスハラによる時間の浪費や離職率の向上などでリソースが不足し業務全体が滞るなどの課題があります。
ブランドイメージの低下
企業のブランドイメージを傷つけるカスハラ行為によって、大きな損失を被る可能性もあります。
- SNSなど口コミ投稿などで、嘘の情報や名誉棄損に該当する誹謗中傷を書き込む
- 会社・社員の信用を毀損させる行為
- 頻繁に来店し、その都度迷惑行為が行われる
これらの行動によって企業の評判が落ち、ビジネスの機会損失が起こることがあります
他の顧客への被害
特に、小売店や飲食店など不特定多数の顧客が出入りする現場でのカスハラは、他の利用客の利便性を損なわせ、ストレスを感じさせてしまいます。
- 店内で大声で叫ぶなどし、秩序を乱す
- 従業員がクレーム対応に追われ、他の顧客の対応が後回しになる
来店するほかの顧客の利用環境や雰囲気を悪化させる行為で従業員のみならず、無関係の人たちへの影響も考えられます。
3. カスハラ対応マニュアルを作成する上で注意すること

✅ハラスメントの定義、判断基準を明確に
ハラスメントや悪質なクレームの定義を明確に設定し、全ての従業員が明確な判断基準を持つことが大切です。
- 具体的な行為例: 現場のスタッフへのヒアリングも行い、起こりやすいハラスメントの具体例をピックアップします。
- 行為の頻度や強度: 一回の行為だけでなく、繰り返される行為や、強度が強い行為もカスハラに該当する可能性があることを明確にします。
- 行為の目的: 従業員を精神的に追い込む、仕事上の不利益を与えるなど、行為の目的が重要であることを示します。
- 客観的な判断基準: 従業員が主体的に判断できるよう、客観的な判断基準を設けます。例えば、「合理的な範囲を超えた要求」や「業務遂行上必要のない行為」などです。
✅従業員への周知の徹底
新しく設定したマニュアルをもとに、従業員への周知を徹底し、認識の統一を行っていきましょう。
- 多様な方法での周知: 社内報、メール、ポスター、研修など、様々な方法で周知徹底を行います。
- 定期的な研修の実施: ハラスメント防止に関する研修を定期的に実施し、知識のアップデートと意識向上を図ります。
- ロールプレイング: 実際に起こりうる状況を想定したロールプレイングを行い、対応方法を身につける機会を提供します。
- 相談しやすい雰囲気づくり: 相談しやすい雰囲気づくりを行い、従業員が気軽に相談できる体制を整えます。
✅社内でカスハラに関する相談窓口を設置する
現場の従業員だけで対応せず、企業で相談窓口を設けておくことで対応者の負担が軽減するだけではなく、問題がこじれることを防ぐことが出来ます。
- 専門性の高い相談窓口: 専門知識を持つ担当者を設置し、報告・連絡・相談を徹底することで、現場と連携をとり最適な対処を実施します。
- 外部機関との連携: 必要に応じて、外部機関(労働局など)と連携し、専門的なアドバイスを受ける体制を整えます。
✅ハラスメント事案のデータを集める
ハラスメントの事案は、貴重なデータです。どのような状況で発生したのかや人物の情報を保持してマニュアルを更新し続けることが重要です。
- 事案の記録: ハラスメント事案が発生した場合、詳細な記録を作成します。
- データの分析: 収集したデータを分析し、傾向や問題点を把握します。
- 再発防止策の検討: 分析結果に基づき、再発防止策を検討し、マニュアルに反映させます。
4. まとめ

カスハラは、従業員に大きな負担をかけ、企業にも多大な損失をもたらす深刻な問題です。カスハラ対策として、マニュアルを作成し、従業員への周知徹底を行うことが重要です。
マニュアルには、カスハラの定義、具体的な事例、対応フロー、相談窓口など、詳細な内容を盛り込む必要があります。また、定期的な見直しや、従業員への研修を実施することで、より効果的な対策が期待できます。
▽補助金・助成金申請に関する無料相談を実施中!
#おすすめ研修
株式会社KMCホールディングスの研修サービス