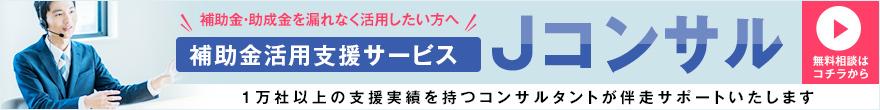2025|両立支援等助成金の概要&申請方法を解説
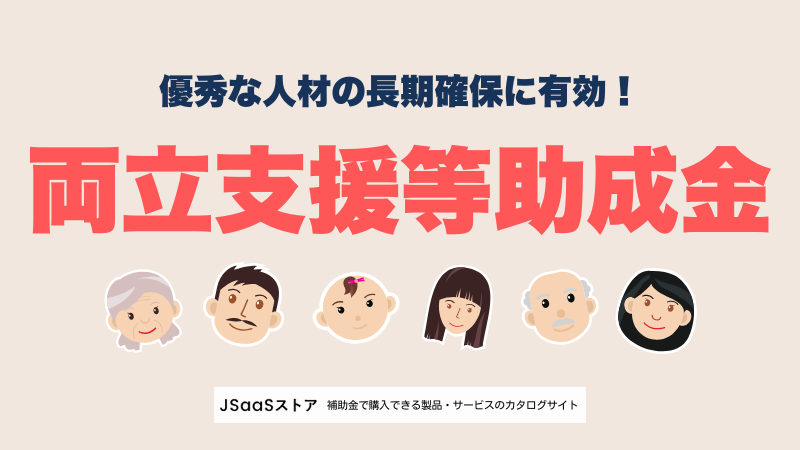
少子高齢化が進む日本において、優秀な人材の確保・定着は企業にとって重要な課題となっています。「両立支援等助成金」は、従業員が安心して働き続けられる職場環境づくりを後押しし、企業の成長をサポートすることを目的としています。
本記事では、助成金の概要から、具体的なコース内容、申請方法、注意点までを詳しく解説します。
▽「補助金&助成金 対象商品」が見つかる!
ー目次ー
1. 両立支援等助成金とは

両立支援等助成金は、仕事と育児・介護等の両立支援に取り組む事業主を応援する制度です。
優秀な人材を確保・定着させることを目的としており、従業員が安心して働くことができる職場環境づくりを後押しします。対象は中小企業事業主で、コースは以下の通りです。
- 出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
- 介護離職防止支援コース
- 育児休業等支援コース
- 育休中等業務代替支援コース
- 不妊治療両立支援コース
- 柔軟な働き方選択制度等支援コース
これらのコースでは、雇用環境の整備や業務体制の整備、育児休業等の取得状況に応じて助成金が支給されます。
「くるみん認定」「プラチナくるみん認定」とは?
「くるみん認定」とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、子育てサポートに関する高い水準の取組を実施している企業に対して、厚生労働大臣が特例認定を行うものです。
さらに、くるみん認定を受けた企業がより高い水準の取組を行い、一定の基準を満たした場合、厚生労働大臣の特例認定「プラチナくるみん認定」を受けることができます。
認定を受けることで、支給人数制限の拡充や支給額が割増されるなどの優遇を受けられる可能性があり、社会的な評価や企業イメージの向上にも役立ちます。
▽この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
2. 両立支援等助成金のコース別概要

2025年3月28日時点で発表されている両立支援等助成金のコースの概要をまとめました。
助成金の支給を受けるためには、就業規則や労働協約・育児休業申出書・雇用環境整備に関する書類など、複数の書類を添付して申請する必要がありますのでそれぞれのコースの概要を理解し、事前準備を行いましょう。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
出生時両立支援コースは、男性労働者の育児休業取得を促進し、仕事と育児の両立を支援することを目的とした両立支援等助成金の一つのコースです。
このコースは、事業主が以下のような取り組みを行った際に支給されます。出典|厚生労働省
【第1種】雇用保険の被保険者である男性労働者が、対象となる子の出生後8週間以内に開始する連続した5日以上(申出に係る4日以上が所定労働日に対する休業であること)の育児休業を取得した場合。
【第2種】第1種の要件を満たした事業年度に育児休業を取得した男性労働者がおり、かつ、当該事業年度における男性労働者の育児休業取得率が、一定の目標値を達成した場合。
助成額は以下の通りです。()内の金額は生産性要件を満たした場合の支給額
【第1種】20万円
代替要員加算:20万円※代替要員を3人以上加算した場合には45万円
【第2種】第一種の受給後、年度ごとの育児休業取得率の上昇率に応じて異なる
- 1事業年度以内に30ポイント上昇:60万円(75万円)
- 2事業年度以内に30ポイント上昇:40万円(65万円)
- 3事業年度以内に30ポイント上昇:20万円(35万円)
介護離職防止支援コース
介護離職防止支援コースは、労働者が家族の介護を行いながら働き続けることができるよう支援する事業主を対象とした助成金制度です。
要件は以下のようなものがあります。出典|厚生労働省
【休業取得時】休業や復帰を円滑にするための「介護支援プラン」(労働者ごとに事業主が作成する実施計画)を作成しプランに基づき介護休業を取得させた場合
【職場復帰時】休業取得時の対象労働者の同一の介護休業について職場復帰させた場合
【介護両立支援制度】介護プランを作成し、プランに基づき介護の為の短時間勤務制度や介護休暇制度などの介護と仕事の両立ができる制度を利用させた場合
助成額は以下の通りです。()内の金額は生産性要件を満たした場合の支給額
【休業取得時】28.5万円(36万円)/1年度5人まで
【職場復帰時】28.5万円(36万円)/1年度5人まで
【介護両立支援制度】28.5万円(36万円)/1年度5人まで
育児休業等支援コース
育児休業等支援コースは、労働者が円滑に育児休業を取得し、職場復帰することを支援する事業主を対象とした助成金制度です。
このコースは、主に「育休取得時」と「職場復帰時」の2つの段階における事業主の取り組みを支援するもので、同一労働者の同一の育児休業について、「育休取得時」と「職場復帰時」の両方の助成金を同時に受けることはできません。
要件は以下のようなものがあります。出典|厚生労働省
【休業取得時】
- 対象育児休業取得者の育児休業等の開始日の前日までに、対象育児休業取得者の上司又は人事労務担当者と対象育児休業取得者が面談を実施し、「面談シート」および、当該面談結果を踏まえたプランを作成していること
- 対象育児休業取得者の育児休業等の開始日の前日までに、作成したプランに基づいて業務の引継ぎを実施させていること
- 対象育児休業取得者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業を含め連続3か月以上)を取得させていること
- 対象育児休業取得者を、当該育児休業等の開始日において雇用保険被保険者として雇用していること
- 育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度を規定していること
- 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、労働局に届け出ていること(プラチナくるみん認定を受けた事業主を除く)
【職場復帰時】
- 対象育児休業取得者の育児休業終了前に、対象育児休業取得者の上司又は人事労務担当者と対象育児休業取得者が面談を実施し、結果を「面談シート」に記録していること
- プランに基づく措置を実施し、対象育児休業取得者が職場復帰するまでに、対象育児休業取得者の育児休業中(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には、産後休業中を含む)の職務や業務内容に関する情報及び資料の提供を実施していること
- 原則として対象育児休業取得者を原職等に復帰させること(育児休業前に無期雇用だった労働者が、休業後有期雇用等として新たに雇用契約を締結している場合は除く)
- 対象育児休業取得者を、育児休業終了日の翌日から起算して6か月以上継続して雇用しており、かつ支給申請日において雇用保険被保険者として雇用していること
- 当該6か月の間に雇用形態や給与形態の不合理な変更を行っていないこと
助成額は以下の通りです。
【休業取得時】30万円/有期雇用労働者1人、無期雇用労働者1人の計2人まで
【職場復帰時】30万円/有期雇用労働者1人、無期雇用労働者1人の計2人まで
育休中等業務代替支援コース
育休中等業務代替支援コースは、2024年1月に新設したコースで、育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給や育児休業取得者の代替要員の新規雇用を実施する事業主を対象とした制度です。
要件は以下のようなものがあります。出典|厚生労働省
【育児休業(手当支給等)】育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
【短時間勤務(手当支給等)】3歳未満の子を養育する労働者が育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
【新規雇用(育児休業)】育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
助成額は以下の通りです。
【育児休業(手当支給等)】以下の合計額
- 業務体制整備経費: 5万円。育児休業期間が1か月未満の場合は2万円。
- 業務代替手当: 業務代替者に支給した手当の総額の3/4(プラチナくるみん認定事業主は4/5)。上限は10万円/月で、代替期間12か月分までが対象です。
- 1事業主1年度につき、~の合計で10人まで、初回の対象者が出てから5年間が上限です。くるみん認定を受けた事業主は令和10年度まで延べ50人を限度に支給されます。
【短時間勤務(手当支給等)】以下の合計額
- 業務体制整備経費: 2万円。
- 業務代替手当: 業務代替者に支給した手当の総額の3/4。上限は3万円/月で、子が3歳になるまでの期間が対象です(支給申請は1年ごと)。
- 1年度につき、本コース全体で1事業主あたり、対象労働者延べ10人までが上限です。くるみん認定を受けている場合は特例があります。
【新規雇用(育児休業)】育児休業期間中に業務代替した期間に応じて以下の額が支給されます。
- 7日以上14日未満:9万円 <11万円>
- 14日以上1か月未満:13.5万円 <16.5万円>
- 1か月以上3か月未満:27万円 <33万円>
- 3か月以上6か月未満:45万円 <55万円>
- 6か月以上:67.5万円 <82.5万円>
1事業主1年度につき10人までが上限です。くるみん認定を受けている場合は特例があります。
不妊治療両立支援コース
不妊治療両立支援コースは、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主を対象とした制度です。
要件は以下のようなものがあります。出典|厚生労働省
- 不妊治療休暇・両立支援制度について、労働協約又は就業規則に規定している場合
- 労働者が不妊治療休暇・両立支援制度を利用しやすい職場風土の取組として、企業トップが制度の利用促進についての方針を全労働者に周知している場合
- 両立支援担当者を、対象労働者が不妊治療休暇・両立支援制度の利用開始日の前日までに選任し、相談に対応している場合
- 対象労働者について、両立支援担当者が把握した後、対象労働者による当該制度の利用開始日の前日までに、対象労働者と少なくとも1回以上プラン策定のための面談を実施した上で結果を記録し、プラン(不妊治療と仕事との両立支援面談シート兼不妊治療両立支援プランを策定し、支給申請に係る不妊治療休暇・両立支援制度及びその利用期間が確認できるようにした場合
助成額は以下の通りです。
- 環境整備、休暇の取得等に該当する場合:中小企業事業主 30万円。
- 長期休暇の加算に該当する場合:中小企業事業主 30万円。
環境整備、休暇の取得等の対象労働者について、長期休暇の加算の支給要件を満たす場合は、長期休暇の加算の対象労働者ともすることができます。
柔軟な働き方選択制度等支援コース
柔軟な働き方選択制度等支援コースは、働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、子が3歳以降小学校就学前までの労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入し、制度の利用者を支援する取組を行った中小企業事業主を対象とした制度です。
要件は以下のようなものがあります。出典|厚生労働省
- 育児休業・短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定している企業
- 一般事業主行動計画を策定し、管轄労働局長に届け出ており、申請時において当該行動計画が有効な場合
- ①始業時刻等の変更②育児のためのテレワーク等③短時間勤務制度④保育サービスの手配及び費用補助⑤子を養育するための有給休暇制度の5つのうち2つ以上の制度を規定している場合
助成額は以下の通りです。
- 制度利用者1人当たり20万円
- 始業時刻等の変更・育児のためのテレワーク等・短時間勤務制度・保育サービスの手配及び費用補助・子を養育するための有給休暇制度の5つのうち2つ以上の制度を導入した場合は1人当たり25万円
- 1中小企業事業主当たり、1年度に支給要件を満たし、かつ制度の利用開始日から起算して6か月を経過した労働者について、上記とあわせて5人までを対象
3. 両立支援等助成金の申請方法と必要書類

助成金は補助金制度と異なり、申請要件をすべてクリアすれば必ず受給することが出来る制度です。対象コースの条件や必要書類等をしっかりと確認し、着実な採択の為の準備をしましょう。
主な必要書類
必要書類は、申請コースによって異なりますが、以下のようなものが必要となります。
- 支給申請書(各種コースの支給申請書はフォーマットが用意されていますので、公式ホームページをご確認ください。)
- 労働協約または就業規則、関連する労使協定
- 措置を実施したこと、実施日が分かる書類
- 面談シート・支援プラン
- 対象労働者の雇用契約書、労働条件通知書
- 対象労働者の出勤簿またはタイムカード及び賃金台帳
- 対象労働者の雇用契約書または労働条件通知書及び会社カレンダー、勤務シフト表 など…
申請方法
両立支援等助成金の申請方法には、電子申請と郵送の2種類があります。
電子申請の場合、厚生労働省が提供するオンラインシステムを利用して申請を行います。支給要件確認申立書(共通要領様式第1号)の添付が不要になるというメリットがあります。電子申請をする前にGビズIDを取得する必要があります。
郵送申請の場合、厚生労働省のウェブサイト等から、申請する助成金コースの支給申請書、支給要領、および必要な様式をダウンロードして申請書に必要事項を正確に記入・押印します。郵送する際は、簡易書留など配達記録が残る方法で行い、申請期限までに必着するように送付する必要があります。
4. 両立支援等助成金を受給するための注意点

両立支援等助成金は、雇用環境の整備で優秀な人材の確保に役立ちますが、受給の条件は細かく定められており申請の難易度が高い制度です。
受給完了後に申請内容の不正が認められた場合、支給された助成金の全部または一部の返還や、他の雇用保険二事業関係助成金も含めた助成金の5年間の支給停止など、厳しいペナルティを受けることがあるため申請の際には細心の注意が必要です。
普段からの適切な労務管理
両立支援制度の申請時には、従業員の労働時間や賃金、出勤状況などを証明する書類の提出が求められます。
日々の勤怠管理を徹底し、労働時間や休日休暇などを正確に記録しておくことが不可欠です。また、労働関係法令を遵守し、適正な労働条件を設定することも重要です。
例えば、育児・介護休業法に基づく休業制度や短時間勤務制度などを適切に運用し、従業員の権利を保護する必要があります。これらの対応を怠ると、申請時に必要な書類が不足したり、制度の対象外となる可能性が生じます。普段から適切な労務管理体制を構築し、記録をしっかりと残しておくことで、スムーズな申請と受給につながります。
従業員への周知の徹底
両立支援制度は、従業員が制度の内容や利用方法を十分に理解していなければ、有効に活用することができません。
制度の概要や申請方法、利用条件などを従業員に周知し、誰もが利用しやすい環境を整えることが重要です。周知の方法としては、社内報やWebサイトへの掲載、説明会の開催などが考えられます。
また、制度を利用する従業員が、上司や同僚から不当な扱いを受けることのないよう、企業全体で理解を深めることも大切です。相談窓口を設置し、従業員が気軽に相談できる体制を構築することも有効でしょう。制度の利用を促進し、従業員のワークライフバランスを支援するためには、積極的な情報提供と理解促進が不可欠です。
制度や支援プランの遵守
両立支援制度を利用する際には、申請した制度や支援プランを遵守する必要があります。例えば、育児休業の期間や短時間勤務の条件などを守ることはもちろん、介護休業の場合なども、プランに基づいた従業員への支援を実行する必要があります。
制度や支援プランを遵守しない場合、助成金の返還を求められたり、今後の利用が制限される可能性もあります。
制度や支援プランの内容をよく理解し、計画的に利用することが重要です。また、状況の変化に応じて、柔軟に計画を見直すことも大切です。必要に応じて、人事担当者や専門家に相談しながら、適切な対応を行いましょう。
▽この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます
パートから正社員に転換するための助成金|申請方法と受給条件を解説
5.補助金対象商品を探すならカタログサイト「Jsaasストア」
Jsaasストアは、中小企業・小規模事業者向けの補助金・助成金が使える商品のカタログサイトです。
あらゆる業種に対応した設備投資・内装工事・ITツール・システム開発・広告宣伝・研修などのサービスが、最大75%オフの価格で購入可能です!
まずは気になる商品をカートに入れてまとめて問合せボタンをクリック!無料で補助金申請できるかどうかの診断結果をお伝えします。
公的制度の申請サポート実績豊富な弊社株式会社ライトアップから補助金申請~採択後の購入までの支援を実施していますので、ぜひチェックしてみて下さい♪
6. 補助金・助成金の無料相談窓口

少子高齢化に伴い人材確保が難しくなっている中小企業が、優秀な人材を長期にわたって確保できるよう仕事と育児・介護等の両立支援にかかる費用を助成する「両立支援等助成金」をご紹介しました。
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース、育休中等業務代替支援コース、不妊治療両立支援コース、柔軟な働き方選択制度等支援コースの6つの中から、御社にピッタリの申請コースを活用するために設定された要件をクリアし、必要書類を正確に準備する必要があります。
そこで活用してほしいのが全国47都道府県、1万社以上の企業の補助金・助成金申請をサポートしてきたJコンサルです!
採択数国内トップクラス!7,000件の公的支援制度データを保有しており、様々な制度の申請サポートが可能です。
💭「両立支援等助成金を活用したいけど、何から手を付けたら良いかわからない…」
💭「他に活用できる制度はないの?」
など、申請にあたって疑問やお悩みがある方は、お気軽にJコンサルの無料相談窓口をご活用ください!
※おすすめ研修
株式会社ReEntry
製造・建設業界のAI化に向けた研修を販売しています。
https://lms.jirei.jp/reentry/

2.png)