AIセミナーはどう選べばいい?ポイントを解説!
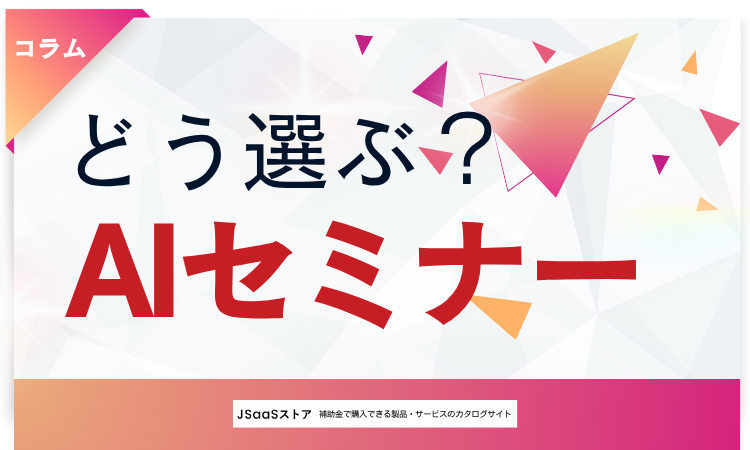
生成AIやChatGPT、画像認識や自然言語処理など、AIのビジネス活用は年々加速しています。それに伴い、AI関連のセミナーや研修も数多く開催されるようになりました。
しかし、実際に参加してみると「内容が初歩的すぎた」「実務に結びつかなかった」という声も少なくありません。
限られた時間と費用を投資するからには、セミナー選びの段階で目的やレベルに合致しているかを見極めることが大切です。この記事では、2025年にAIセミナーを選ぶ際に押さえておきたい基準を解説します。
▽「補助金&助成金 対象商品」が見つかる!
1. AIセミナーの種類と特徴を理解する
AIセミナーには、大きく分けて「入門型」「技術習得型」「事例研究型」「経営戦略型」といった種類があります。
入門型はAIの基本概念や最新動向を広く学びたい人に向き、技術習得型はエンジニアやデータ分析担当者が具体的なツール・手法を学ぶのに適しています。事例研究型は他社の取り組みを参考にしたい経営者に、経営戦略型は「自社の事業にどう組み込むか」を考える経営層に効果的です。まずは自分の立場と目的に合ったタイプを絞り込みましょう。
2. 目的に合ったテーマ設定がされているかを確認する
「生成AIを使ったマーケティング活用」「工場の生産効率改善」「中小企業のバックオフィス自動化」など、セミナーごとにテーマは異なります。
自社が抱える課題に近いテーマが設定されているかを確認することが、最大の成果につながります。
3. 登壇者・講師の専門性と実績を見極める
AI関連は流行性が強く、講師の知識や実績に差が出やすい分野です。登壇者が大学研究者なのか、企業の実務家なのか、それともコンサルタントなのかによって学べる内容は大きく変わります。
経営に応用したいなら実務経験豊富な企業講師が望ましく、技術を深めたいなら研究者やエンジニア講師が適しています。
4. 実践型か理論型か、学びのスタイルを考える
セミナーの中には「座学中心で理論解説に終始するもの」と「ワークショップ形式で実際にAIツールを操作するもの」があります。
例えば、ChatGPTを業務で使うセミナーでは、実際に質問を入力して業務文書を生成する体験が含まれていると、翌日からの活用に直結しやすいでしょう。
一方で戦略立案や経営判断に役立つのは、理論型のマクロ視点セミナーです。
5. 自社課題との関連性と持ち帰れる成果を意識する
「セミナーに参加して終わり」にならないために、事前に「この課題を解決するヒントを得たい」と明確に目的を設定しておくことが重要です。
また、配布資料の充実度やフォローアップ体制(録画配信・追加教材・講師への質問機会)があるかどうかも確認ポイントです。これらが揃っていれば、自社への落とし込みやすさが格段に高まります。
6. まとめ:選び方の基本は「目的 × 実務への落とし込み」
AIセミナーを選ぶ際には、単に「話題だから参加する」ではなく、目的・テーマ・講師・形式・成果物の5つを事前に確認することが重要です。自社の業務改善や新規事業創出に役立つかどうかを判断基準にすれば、時間も費用も有効に投資できます。
AIの進化は速いため、2025年も最新情報をキャッチアップできるセミナーは価値がありますが、その中でも「自分にとって何を持ち帰れるか」を意識して選ぶことが成功の秘訣です。
▽「補助金&助成金 対象商品」が見つかる!

2.png)