中小企業にも義務化されたハラスメント対策とは?
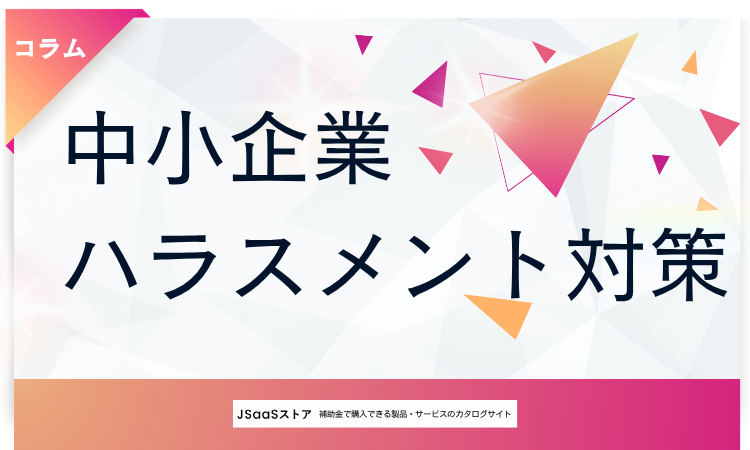
近年、職場におけるハラスメント対策は「努力義務」から「法的義務」へと変化しています。特に中小企業では、2022年4月からハラスメント防止措置が義務化され、対応を怠ると行政指導や企業イメージ低下のリスクが生じます。本記事では、中小企業が実施すべきハラスメント対策の内容と、実務上のポイントをわかりやすく解説します。
ー目次ー
1. 中小企業にも義務化されたハラスメント対策とは
法改正の概要(改正労働施策総合推進法)
2020年6月に施行された「改正労働施策総合推進法(通称:パワハラ防止法)」により、企業は職場のパワーハラスメント防止措置を講じることが義務化されました。当初は大企業のみを対象としていましたが、2022年4月から中小企業にも義務化されています。
義務化の対象と時期
中小企業もすべての業種・業態が対象です。厚生労働省は、ハラスメント対策の義務化を「職場の健全な人間関係構築」と「労働者の安心感向上」を目的としています。
2. 中小企業が対応すべき具体的なハラスメント対策
① 相談窓口の設置
従業員が安心して相談できる体制を整えることが基本です。相談担当者を明確にし、匿名での相談も受け付けられるようにします。外部専門家(社労士・弁護士)への委託も有効です。
② 社内方針・ルールの明文化
ハラスメント行為を許さないという企業方針を就業規則や社内規程に明記し、社内に周知します。特に「行為の定義」「懲戒の対象」「相談手順」などを明文化しておくことが重要です。
③ 研修・啓発活動の実施
従業員・管理職向けの研修を実施し、具体的な事例を通じて意識を高めます。厚生労働省が公開している「職場のハラスメント対策企業向けマニュアル」を参考にするのも有効です。
3. ハラスメントの種類と典型的な事例
パワーハラスメント
上司が部下に対して、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動を行う行為です。例として「人格を否定する発言」「過大なノルマの強要」「他の社員の前での叱責」などが挙げられます。
セクシュアルハラスメント
性的な言動により労働者が不快感を覚え、職場環境が悪化する行為です。冗談のつもりでも被害につながる場合があるため、日常的な言葉遣いにも注意が必要です。
マタニティ・育児関連ハラスメント
妊娠・出産・育児休業を理由に不利益な扱いをする行為です。近年では、男性育休取得者へのハラスメントも問題視されています。
4. 義務違反のリスクと企業への影響
行政指導・公表制度
義務を怠った企業には、労働局からの指導・勧告が行われ、従わない場合は企業名が公表されることもあります。特に相談体制を整えていない場合は注意が必要です。
企業イメージ・採用への悪影響
ハラスメント問題が発覚すると、SNSや口コミで企業イメージが大きく損なわれる可能性があります。離職率の上昇や採用難にもつながるため、日常的な防止体制の構築が欠かせません。
5. まとめ:法令遵守と職場環境改善を両立させる
中小企業にとってハラスメント対策は、法令遵守だけでなく「人材定着」「企業の信頼性向上」にも直結します。相談窓口の設置・社内ルールの整備・研修の実施を進め、安心して働ける職場づくりを実現しましょう。
▽「補助金&助成金 対象商品」が見つかる!

2.png)